医師紹介
Doctors
伊藤 裕章 いとう ひろあき
院長/医学博士/内科医師
- 経歴
-
- 大阪大学医学部卒業
- 昭和55年 7月 大阪大学医学部附属病院第三内科研修医
- 昭和56年 7月 大阪大学医学部附属病院特殊救急部研修医
- 昭和56年 9月 聖隷三方原病院診療部外科医師
- 昭和57年 7月 兵庫県西宮病院外科医師
- 昭和58年 1月 大阪府済生会富田林病院内科医師
- 昭和59年 7月 石井記念愛染橋病院内科医長
- 平成 4年 8月 大阪大学医学部内科学第3講座助手
- 平成 6年 9月 米国スタンフォード大学免疫リウマチ学教室留学
- 平成15年 3月 大阪大学大学院分子病態内科学講座講師
- 平成17年 7月 大阪大学大学院消化器内科学講座講師
- 平成18年 1月 田附興風会 医学研究所北野病院消化器センター部長
- 平成22年 4月 医療法人錦秀会 インフュージョンクリニック院長
- 資格・所属学会
-
- 日本消化器病学会認定専門医
- 日本消化器内視鏡学会指導医
- 日本内科学会認定内科医
- 日本消化管学会胃腸科認定医
- 厚生労働省難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班研究協力者
- 米国消化器病学会会員
- 米国免疫学会会員
- 雑誌「IBD Research」編集委員
院長挨拶
「インフュージョンクリニック」と聞いても、ピンとこない方が多いかも知れませんね。
炎症性腸疾患は消化管に炎症をおこす病気、これに対しリウマチは関節に炎症をおこす病気と、一見無関係のように思われますが、実は病気の成り立ちがとてもよく似ていて、そのために治療も共通点が多いのです。
近年生物学的製剤(抗体医薬:例えば、レミケード・アクテムラ等)がこれらの治療に導入され、患者さんの「生活の質(QOL)」を飛躍的に向上させています。もっとわかりやすく言えば入院や手術を減らせるということです。これらの薬は点滴投与されることが多いため「インフュージョン(点滴)クリニック」と名付けました。
もちろん、私たちの施設はインフュージョン治療を受けない方も、炎症性腸疾患・リウマチの専門的な知識と経験を活かして、必要な時に必要な治療を行っていきます。
生物学的製剤は多くの場合、副作用もなく安全に投与できますが、一種のアレルギー反応を起こしてしまうこともあります。私たちは年間1,800件の投与経験があり、投与時反応に対する処置や予防に関するノウハウを蓄積しています。投与時反応のために治療が継続できなくなる可能性は極めて低く、このノウハウを活かして、安全にこの新しい治療をひとりでも多くの患者さんに受けて頂けるようにと考えています。
さらに一般内科診療、保険ではカバーされないものの健康の増進に役立つと思われる診療(特別診療)、心理カウンセリングなどを行っています。
「医療法人錦秀会 インフュージョンクリニック」を、どうぞよろしくお願いいたします。
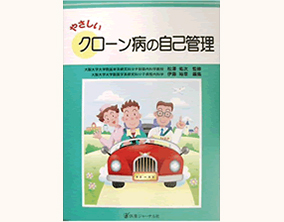
『やさしいクローン病の自己管理』
伊藤裕章編集 医薬ジャーナル社/2003年
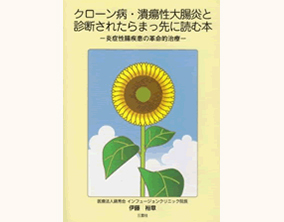
『クローン病・潰瘍性大腸炎と診断されたらまっ先に読む本―炎症性腸疾患の革命的治療』
伊藤裕章(著) 三雲社/2012年
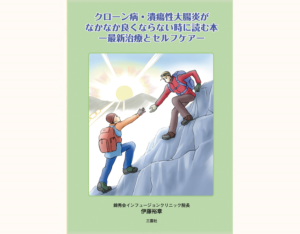
『クローン病・潰瘍性大腸炎がなかなか良くならない時に読む本-最新治療とセルフケア』
伊藤裕章(著) 三雲社/2023年
有光 晶子 ありみつ しょうこ
内科医師
- 経歴
-
- 平成11年 3月 東京女子医科大学医学部卒業
- 平成11年 4月 大阪大学医学部附属病院第一内科研修医
- 平成11年 6月 大阪府立急性期総合医療センター研修医・レジデント
- 平成15年 6月 大阪府立急性期総合医療センター消化器代謝内科 医員
- 平成17年10月 済生会千里病院内科 医員
- 平成23年 4月 医療法人錦秀会インフュージョンクリニック 医長
- 資格・所属学会
-
- 日本消化器病学会認定専門医
- 日本炎症性腸疾患学会IBD専門医
- 日本内科学会認定内科医
- 日本消化器内視鏡学会会員
- 日本母性内科学会会員
こんにちは。クリニックの患者さまが、学生生活や就労生活、家庭生活を楽しく過ごせるように、また、受験、就職、チャンスのお仕事、結婚、出産など「人生のここ一番!」に踏ん張れるよう、院長とともに医療の面からサポートさせていただきます。炎症性腸疾患(IBD)をお持ちの方が、将来の妊娠や出産について安心して考えられるよう、「プレコンセプションケア外来(プレコン外来)」も行っています。
なんでもお話しください。一緒に解決していきましょう。
柿本 一城 かきもと かずき
- 専門
-
- 内科
原 あずさ はら あずさ
- 専門
-
- 内科
荻野 崇之 おぎの たかゆき
- 専門
-
- 外科
甲斐 康之 かい やすゆき
- 専門
-
- 外科
関戸 悠紀 せきど ゆうき
- 専門
-
- 外科
根津 理一郎 ねづ りいちろう
- 専門
-
- 特別診療
リウマチ・膠原病内科(免疫内科)、皮フ科
嶋 良仁 しま よしひと
特任教授/内科医師
- 経歴
-
- 昭和63年 埼玉医科大学医学部医学科卒業
- 平成 7年 医学博士(大阪大学)
- 平成10年 ハーバード大学医学部ポストドクトラルフェロー
- 平成15年 大阪大学医学部助手
- 平成19年 大阪大学大学院医学系研究科 助教
- 平成27年 大阪大学大学院医学系研究科 講師
- 平成30年 大阪大学大学院医学系研究科 特任教授
- 資格・所属学会
-
- Infection control doctor(ICD)(日本感染学会)
- 日本内科学会認定内科医
- 日本内科学会認定総合専門医
- 日本リウマチ財団登録医
- 日本リウマチ学会専門医
- 日本リウマチ学会指導医
- 身体障碍者福祉法第7条認定医「肢体不自由」および「免疫障害」
- 所属/学位
-
- 大阪大学 大学院 医学系研究科 所属
- 医学博士(大阪大学)
整形外科
冨田 哲也 とみた てつや
教授/整形外科医師
- 経歴
-
- 昭和63年 3月 大阪大学医学部医学科卒業
- 昭和63年 7月 大阪大学医学部附属病院 医員
- 平成 1年 1月 行岡病院 整形外科医員
- 平成 2年 1月 大阪厚生年金病院 整形外科医員
- 平成 3年 1月 国立白浜温泉病院 整形外科医員
- 平成 7年 3月 大阪大学大学院医学系研究科博士課程修了
- 平成 7年11月 大阪大学医学部 整形外科非常勤医員
- 平成 7年12月 大阪大学医学部整形外科 助手
- 平成14年 4月 米国Stanford大学Research Fellow
- 平成15年12月 大阪大学大学院医学系研究科 助手復職
- 平成19年 9月 大阪大学大学院医学系研究科 学部講師
- 平成21年10月 大阪大学大学院医学系研究科 寄附講座准教授
- 令和 4年 4月 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科教授
- 資格・所属学会
-
- 日本整形外科学会
- 日本リウマチ学会(評議員)
- 日本炎症・再生学会(評議員)
- 日本抗加齢学会(評議員)
- 日本人工関節学会
- 日本脊椎関節炎学会(理事)
- 日本リウマチ財団(理事)
- アメリカ整形外科学会
- アメリカリウマチ学会
- American Association of Hip and Knee Surgeons
- Editorial Board of Journal of Arthroplasty
- 厚生労働省難治性疾患政策研究事業脊椎関節炎研究班班長(H28-)
- ASAS (Assessment of Spondyloarthritis International Society) Full member (2019/1-)
- 日本リウマチ財団教育研修委員会委員長(R2/9-)
- 2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員デイレクター(2021/5-)
- 認定医等の資格
-
- 日本整形外科学会専門医
- 日本整形外科学会リウマチ専門医
- 日本リウマチ学会指導医、認定医
- 日本リウマチ財団登録医
- 日本人工関節学会専門医
- 受賞歴
-
- 平成11年 日本整形外科学会奨励賞
- 平成11年 日本骨代謝学会優秀演題賞
- 平成12年 日本炎症学会奨励賞
- 平成19年 JOA-AOA traveling fellow
- 平成20年 日本抗加齢医学会優秀演題賞
- 平成24年 脳/心/血管抗加齢研究会Special Investigator Award
- 平成29年 Modern Rheumatology Top reviewer award 2016
以下でお困りではありませんか?
お問い合わせ
CONTACT US
長く付き合う病気だからこそ、
「理解」と「継続」を。
ご相談やご質問など、ご不明点があれば
お気軽にお問い合わせください。


 「臨床研究について」
「臨床研究について」